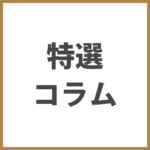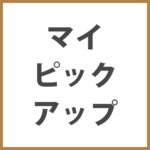SDGsと切り離せない循環型システムの形、アクアポニックス

SDGsにおいて、循環型社会がキーワードになっています。「循環」といっているひとつは、地球の生態系の循環。自然環境と生物で構成されるつながりです。もうひとつは「リサイクル」といわれる物質的な循環。
経済社会のなかで「自然の循環」を壊さないように資源をリサイクルするという意味で、SDGsの目標を達成するためにも「環境・経済・社会」を循環できることが目指す方向性「循環型社会」といわれます。
古代からから存在するアイデア
そんな「循環型」システムが成り立っているといえるような仕組み「アクアポニックス」をご存じでしょうか。魚の水産養殖(Aquaculture)と植物の水栽培(Hydroponics)という2つの言葉を合わせた造語で、魚と植物を水を循環させて両方を育てるシステムです。魚の排出物を微生物が分解し、植物がそれを栄養として吸収、浄化された水を再び魚の水槽へもどす構造を作ります。
メリットとして、水の使用量が少なくてすみ、農地に適さない土壌や、水の資源が乏しい地域でも農業を可能にしてくれます。
アクアポニックスの起源はメキシコの「チナンパ」と呼ばれる農法で、1000年前の古代から存在したアイデア。河の上に”いかだ”上のものを浮かせて、そこで植物を育てていたことがルーツだといいます。
今では、野菜工場といわれるような大規模な設備から、部屋の中における栽培キットまでさまざまな形で循環方法が活用されています。アクアポニックスで育てる野菜は、化学肥料を使用しないため、安全なオーガニック野菜にもなります。
アクアポニックスは進化している
また、進歩したアクアポニックスとして新たな研究もされています。乾燥した地域の塩分の高い土壌の問題を解決するための栽培方法(鳥取大学農学部 山田 智教授)です。
水資源が乏しい地域でも作物の水耕栽培が可能になるアクアポニックスですが、乾燥した地域では、土壌の塩害問題があります。土に塩分が多くなると、多くの作物は育たなくなり、不毛の地として放置されてしまうのです。
その問題を解決するための活用方法として、塩分を含んだ地下水で飼育可能な魚やエビを養殖し、その排水で塩分を吸収する特性をもつ作物を水耕栽培。塩分を取り除いた水で、ハーブ類やトウガラシ、ミニトマトなどの栽培をする構想です。これは、SDGsの「2.飢餓をゼロに」「6.安全な水とトイレを世界中に」「9.産業と技術革新基盤」「15.陸の豊かさも守ろう」の目標につながり、「環境・経済・社会」を循環するシステムといえると思います。
現代でも持続可能な循環型システムのアイデアは、古代の先人たちから学ぶとでてくるかもしれません。水の資源を守りながら土壌を再生していく。今後のアクアポニックスを活用に期待します。
参考資料
環境省 環境白書
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h29/pdf/
アクアポニックスさかな畑
https://aquaponics.co.jp/history-of-aquaponics/
SATREPS 研究課題
https://www.jst.go.jp/global/kadai/h2605_mexico.html
みなさんの投稿
コメントを投稿するにはログインしてください。